2018年の終活はこう動く
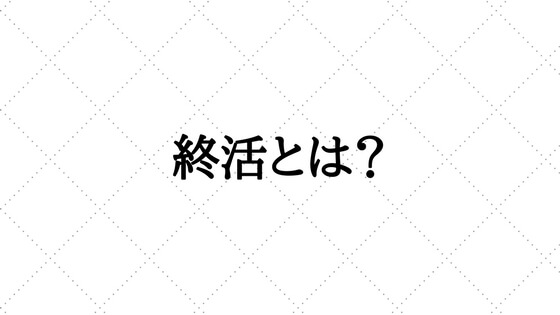
終活とは「人生の終わりをより良いものとするため、事前に準備を行うこと」です。
残される方のためと考えられることも多いですが、自身が人生を見つめ直し、今後を自分らしく前向きに生きるための活動でもあるのです。
2017年はテレビや雑誌で取り上げられることも多くなり、市民権を得た感のある「終活」という言葉ですが、2018年はどのような動きを見せるのでしょうか?
終活の専門家である「終活カウンセラー資格」を持つ筆者が予想します。
所得格差による葬儀の二極化が進む
生きているうちにお世話になった人に感謝を伝える「感謝の会」や「生前葬」は今後も増えていくことでしょう。
「生前葬」を行っても、火葬をしないわけにはいきませんから実質は2回葬儀をすることになります。
金銭的に余裕がある人にしかできないことだと思われます。
逆に「火葬式」などの極端に簡素化された葬儀も増えてくるはずです。
「火葬式」は通夜や告別式を行わず、火葬場でごく簡単な儀式を行うスタイルです。
一番の特徴は金額が安く、15万円から20万円で行うことができます。
一般的な葬式から、家族葬、火葬式など葬儀の幅は広がってきています。
しかし、お金がなくては選べる範囲も狭くなります。
お墓や納骨堂は距離の壁を超えていく
従来の「家制度」のもとでは、墓や納骨堂は子孫が代々守っていくものでした。
しかし、「個」が尊重されるようになった現代では、親世代が子世代に遺骨の管理・供養を任せないという選択肢も出てきました。
寺院や霊園や自治体に毎年の管理料を納めなくてもよい「永代供養」はますます増えていきます。
子世代がお墓の管理をしなくてよければ、自分が好きなところに遺骨を埋葬するという考えも尊重されます。
遺骨を海に撒く「海洋散骨」や、自分の故郷や縁があるところ、景色がいいところに埋葬されたいと思う人の希望も叶えられます。
都心でお墓や納骨堂を手に入れるには数百万円の金額が必要です。
「狭いところに埋葬されるよりも安い金額で大自然に還りたい」という人のニーズに応える供養がどんどんでてくるはずです。
私の知り合いの寺院が運営している熊本県と大分県の県境にある阿蘇「天空陵」では、「永代供養の樹木葬」で税込み40万円という低価格でありながら、戒名をつけてくれ、丁寧な供養をしてくれます。
抜群のロケーションで、九州全域だけでなく全国からの問い合わせ・申し込みが増えてきています。
以前取材した鹿児島の「海洋散骨」も毎月申し込みが増えているそうです。
エンディングノートを書く人が増える
終活の一歩目として、エンディングノートは最適です。
遺言と違い、気軽に購入できること・書き始められることが後押ししています。
当ブログを通しても、毎日エンディングノートが購入されています。
▼一番人気のエンディングノート

コクヨ エンディングノート もしもの時に役立つノート B5 LES-E101
- 出版社/メーカー: コクヨ(KOKUYO)
- 発売日: 2010/09/01
- メディア: オフィス用品
- 購入: 16人 クリック: 236回
- この商品を含むブログ (26件) を見る
エンディングノートの選び方・書き方【おすすめ無料終活ノート紹介】 - きみと終活とわたし
自治体がエンディングノートを配布する事例も増加していくはずです。
事前に葬儀の資料請求をする人も増える
残された家族が、地域や親戚に合わせて決めていた葬式も、生前に自分の意志で決めるケースも増えてきています。
「終活」という言葉が広がり、死の準備をすることのハードルが下がってきているような気もします。
- 自分の葬式をどのような形式にするのか?
- 費用はどれくらいにするのか?
- 誰を呼んで欲しいのか?
この3つが決まっているだけでも親族は助かります。
葬式は生前に自分で見積しないと数十万円の損 - きみと終活とわたしでも書いたように、残された家族に任せると葬儀費用が上がることが多いので、事前に比較検討し、自分である程度のことを決めておくといいでしょう。
葬儀の相見積をする人も増える
葬式は、なかなか複数の葬儀社で比べることが難しいと思われていますが、無料の一括見積ができるサービスの需要も伸びてきています。
手元供養が一般化してくる
まだまだ現代仏壇を買われる方も多いですが、宗教色がなく現代の住宅事情に合っている手元供養も認知されてきています。
手元供養は永代供養との相性もよく、遺骨を中に入れられるものもあります。
移動社会である現代では、生まれた場所と働く場所が違うことがほとんどで遺骨の埋葬先に困る方もいます。
遺骨の大部分を永代供養(合祀)や海洋散骨し、少量を手元供養にして自宅で供養するという方法も一般化してくるでしょう。
▼関連記事
手元供養のメリット・デメリットや種類について専門家が解説 - きみと終活とわたし
終活のメリットとデメリット
一見いいことばかりに見える終活ですが、メリットだけでなくデメリットもあります。
終活のメリット
「残される人に負担を残さない」ということに尽きます。
これは金銭的な面でもそうですし、意思決定の面でもです。
生前に身の丈に合うもので決めておけば、費用は安く済みます。
残された家族が決める場合は、親戚のことや世間の相場を考えながらさまざまなことを行わなければなりません。
また、決断が本当に故人にとって最良のものだったのだろうか?
と悩む方もいらっしゃいます。
終活する本人にとっても、自分の最期のことを準備しておけば、残りの人生を心配なく過ごせるという方もいらっしゃるはずです。
終活のデメリット
故人を供養するということは、故人のためでもあり、残された方の哀しみを癒すということでもあります。
あまりにも本人が生前に準備し過ぎると、残された人の役目が小さくなってしまうことがあります。
葬式の準備や四十九日、納骨などを通し、故人に対して「やれるだけのことはやった」と思えるものです。
あまりにも完璧に終活しすぎてしまうのもよくないかもしれません。
また、「就活」・「婚活」・「妊活」などの言葉といっしょで、世間一般がするものと捉えられるのも非常に迷惑だという考えもあります。
本当は終活するのもしないのも自由なのですが、あまり言葉が強くなり過ぎると、
「うちの親が終活してくれなくて困る」
なんて状態になってしまうかもしれません。
あくまで「したい人がする」というスタンスが大事だと私は思っています。
自分が死ぬことなんて考えたくない人が多数派ですから「終活」という言葉をプレッシャーに感じる人がでてきたとしたら、それはデメリットなのではないかと考えています。
2018年の終活は「多様化」
供養の方法や、葬式にしても選択肢がどんどん増えていくのが2018年の終活の特徴と言えるでしょう。
これは、自分にとって最適なものを選ぶことが難しくなってきているということでもあります。
選択肢が少なければ迷うことも少なかったのですが、これだけ数が増えてくると何を選べばいいいのかがわからなくなってきます。
そんなときのための専門家として、読者の方に有益な情報をお届けできるように頑張ります!!
それでは、2018年もよろしくお願い致します。
▼樹木葬の人気もさらに高まりそうです