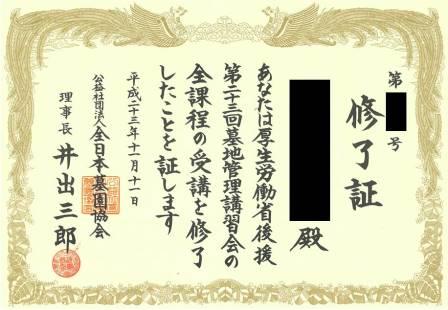寿陵(じゅりょう)とは?

寿陵は「生前墓」とも呼ばれ、生前に立てるお墓のことを言います。
生前にお墓を建てることは、「死ぬ準備をしているようだ」と嫌われる方もいらっしゃいます。
しかし、古来の中国で寿陵は、「長寿」・「子孫繁栄」・「家内円満」の3つの果報をもたらす縁起のよいことと考えられ、生前墓を建てることは慶事(お祝い事)とされていました。
寿陵は、聖徳太子や、秦の始皇帝、昭和天皇や今上天皇も建てていますし、ピラミッドも一種の寿陵と言えるでしょう。
代表的な寿陵
天皇家のお墓
天皇家のお墓は生前に建てられることが多いです。
平成天皇のお墓の建立についても以前ニュースがありました。
秦の始皇帝のお墓
秦の始皇帝お墓である「秦始皇帝陵」も寿陵と言われています。
「兵馬俑」は学校でも習いましたね。
クフ王のピラミッド
クフ王のピラミッドも生前に建てられたという説がありますが正確にはどうかわかりません。
実際の寿陵は宣伝文句の側面も?
実際の寿陵は、民間霊園や石材店の宣伝文句という面もあります。
亡くなった方が出たところだけをターゲット(お客様)とするより、生きている人の方がずっと人数が多いわけですから、知恵を絞った結果、使われているのが「寿陵」という言葉という説もあります。
業者の間では、需要の先食いだったのではと語る人もいます。
お墓を建てるのは、生前(寿陵)と死後のどちらかがいいのか?
それでは、お墓を建てるのは生前と死後、どちらがいいのでしょうか?
「終活カウンセラー」であり、「お墓ディレクター」でもある専門家の筆者の見解は、生前。
つまり「寿陵」をお勧めします。
これは、お墓に限ったことではありません。
納骨堂でも、永代供養・樹木葬、散骨でも同じです。
ご自身の供養される先(納骨される場所)に関しては、生前に意思決定をしておくということが重要です。
「寿陵」つまりは生前に建墓することがいい理由
家族・親族間のもめごとを回避できる
お客様と接する中で、度々でてきます。
亡くなった方のためのお墓を建てるときに、かけてもいいと思う予算が家族間でも相違があるケースがあります。
例えば、ご主人が亡くなった奥様が、立派なお墓を建てたいと思っていても、息子夫婦は、できるだけ安いお墓にして、遺産がたくさんもらえる方がいいと思っているケース。
例えば、奥様はシンプルで安いものにしようとしていたけれど、親戚がお金を出しもしないのに、もっといいものにしろと口を出してくるケース。
本人が決めなかったばっかりに、悩まれるケースがあります。
また、お客様と接する中で感じることがあります。
どなたかが亡くなった後にお墓を建てる場合、
「高いものを建てるのがいい供養になる」
という気持ちになる方が一定数いらっしゃいます。
亡くなった方の遺骨を収めるのは、一般的に四十九日、もしくは一周忌です。
ただでさえ、葬儀のあとで精神的にきつい時期に、供養という大事で、高額な決断を残された人がするということを想像して頂ければ、生前に供養に関することを決定しておくことの重要性がわかって頂けるはずです。
祭祀に関わるものは相続税の対象外でお得
お墓や仏壇など、祭祀に関わるものは相続税の対象外となります。
家族が亡くなり、財産を受け継ぐ場合、相続税が課税されます。
相続税は、現金・預金・不動産・有価証券など、形を問わず全ての財産に対して課税されますが、「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は課税されません。
平成27年にスタートした「新相続税制」。
基礎控除が4割削減されたことで、相続税の対象者が、それまでの約1.8倍、全体の8%になりました。
より多くの資産を家族に残すために、生前に供養に関することを決定することは有効です。
つまり「寿陵は相続に関してはお得」です。
寿陵墓のメリット・デメリット
寿陵墓のメリット
前述したように、家族・親族の精神的な負担が少なくなることや、冷静な判断ができること、相続税の対象にならないということです。
何より、ご本人に最後のひと仕事を終えた充実感があるはずです。
寿陵墓のデメリット
現在、供養の種類・方法は多様化してきています。
さらなる長寿社会を迎えるなか、年数の経過とともに、もっと自分や家族に合った供養の方法が見つかる可能性があります。
また、生前にお墓を建てた場合、少額ではありますが、毎年の管理料を支払わなくてはなりません。
寿陵はお祝いごとで開眼供養をする
お墓の仕事をしていると聞かれることですが、寿陵は慶事です。
紅白饅頭や果物、お花などでお墓を賑やかにして開眼供養(魂入れ)をします。
生前にお墓を建てることは仏教でもよいこととされています。
実際に寿陵を建立したお客様の声
定年後、お墓を建てた佐藤さん
佐藤さんは公務員を定年されました。
次男だったこともあり、お墓を建てることに。
「生前に建立したことで、自分の好きな形で建てることができた。石もインド産のよい石を使用できたので満足している。霊園探しから始まって、お墓が建つまでは4ヶ月かかったので、元気なうちでよかったと思う」
とおっしゃっていました。
最後に
寿陵(生前墓)だけでなく「終活」に関しては、できるだけ元気なうちに情報を集めることをお勧めします。
以前は、地域性が強く選択肢が少なかった「供養」や「葬儀」。
インターネットのおかげで、選択肢は広がってきています。
幅広い情報の中から、ご自身に最適の供養の方法を見つけることを応援できればと思っております。
本日は『寿陵(じゅりょう)とは?寿陵のメリット・デメリット』という内容でした。
それでは。
Mr.Kuyou(筆者)の取得資格 ・ 修了証
終活・お墓・墓地に関連する資格を取得しています。
終活についての情報を更新していきますので、よろしければお気に入りやブックマークにご登録ください。
▼終活カウンセラー

▼お墓ディレクター

▼墓地管理講習会全課程修了証(公益社団法人全日本墓園協会開催)